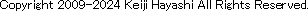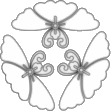新聞・雑誌 掲載記事
人権のひろばNo.73に掲載された記事より
聞き手 東京都連 油井 久仁子
――もっと日本舞踊に親しんでいただくために、"ゆかたde Shall we dance"という新しい試みを始められたと伺いました。
去年は、名古屋と京都で行いました。どれくらい集まっていただけるか不安でしたが、おかげさまで好評で、今年は名古屋、京都に加え、西宮でも開催することが決まっています。
この"ゆかたde Shall we dance"は、「古典のチントンシャンは堅苦しい、盆踊りだけでは物足りない」、そういう方は浴衣で私と一緒に踊りませんか、ということで始めた教室です。文字通り『Shall we dance?』などの曲を、踊りやすく振り付けした日本舞踊で踊っています(笑)。浴衣をお待ちでなかったり、お勤めをされていて荷物を持っていけない場合などは、ジーンズにトレーナー姿でもかまいません。
実は今、みなさんがテレビや舞台でご覧になっている日本舞踊は「洋楽」なのです。チントンシャンの古典の譜面で踊っているのは歌舞伎だけです。宝塚もほとんどの古典をアレンジして、洋楽にして踊っているんですよ。
チントンシャンは、洋楽のようにオタマジャクシ(音符)で完全に譜面に書くことができません。洋楽は、四小節、八小節というふうに分かれて、四拍子なら、一二三四、二二三四、三二三四、四二三四のように拍子をとることができるので、洋楽にアレンジしますと、体でリズムをとって踊りやすくなります。
――そうなのですか。素人考えでは、日本舞踊は体をきちっと作らないと形をとることが難しいように思いますが。
洋舞でも同じですが、普段は使わない特別な筋肉を鍛えていくというか作り上げないと形をとることは難しいです。"ゆかたde Shall we dance"は、形ができるというよりも、日本舞踊が初めての方でも、手順を覚えて踊ることができるような振り付けにしてあります。体を動かして楽しんでいただくことが目的なのです。だんだん振り付けが簡単になってしまい、こんなのでいいのかなと心配になったりすることもありますけれど(笑)、最初から高度な技術を教えようとしても、ついていらっしゃれないでしょうから。
――新しいことをお始めになるのは、冒険で大変なことだと思います。そのお気持ちの若々しさはすごいですね。
いつも何かをしなくてはならないと思っています。家元・林与一に「人様に踊りを教えていくためには、ただ体を動かして表現するだけでなく、自分自身の中から出ていくものを身につけなさい」と言われました。それで、俳優や振り付けの仕事もしています。
私の流派である林流は、歌舞伎俳優・初代中村鴈治郎の長男・林又一郎(林長三郎)が創始しました。現在は、孫に当たる俳優・林与一が家元を継承し、私が分家として門弟の指導をしています。
私は、父・花柳壽晃から日本舞踊を学び、五世・花柳芳次郎に師事いたしまして、十六歳のとき林又一郎の芸養子となりました。
日本舞踊は、心身を通し表現することで、礼儀作法、所作など日本の美の奥深さを感じとることができるものだと思っています。私と一緒に日本の美を希求されるもよし、品格向上、所作、礼儀を求められるもよし、まずは日本舞踊に親しんでいただきたいですね。その第一歩が"ゆかたde Shall we dance"というわけです。 ただし、名古屋、京都などにも、それぞれに日本舞踊の流派がありますので、この試みを始めるに当たり、あいさつに伺って、「林流の林啓二」ではなく、「俳優の林啓二のワークショップ」として開催しています。
――礼節を重んじる伝統の世界ならではのお話ですね。
「礼」は、生きる上で大切なことだと思っています。うちにお稽古に来ている方で、「ほかでお名前をいただいているのですけれど」という方には、「それなら、所作指導を受けるつもりでいらっしゃい」とも言っています。
関西は楽しみでお稽古に来ている方が多いですが、関東ではお芝居の勉強のために来ている方が多いです。林流は、どちらかというと芝居がかった踊りなものですから。
映画やテレビでは、カメラが近くから撮影したりしますので、表情をつけるだけでも「演技」になります。しかし舞台では役者の表情は見えませんから、本当の演技力が要求されます。例えば、お扇子を口のところに持ってきて話しますと、大きな声で台詞を言っても、内緒の話だと観客に伝わります。煙管の持ちかた一つで職業が分かります。所作を勉強することは、大切なことです。
――日本舞踊を続けてこられて、どのようなことをお感じになられますか。
「継続は力なり」、何でもいいから続けることが大切だと実感しています。それと、上杉鷹山の言葉「為せば成る 為さねば成らぬ何事も 成らぬは人の成さぬなりけり」ですね。やってみなければ、そして続けないと何にもなりません。たとえ失敗したとしても、その経験から何かしら得るものがあって、次に取り組むものに活かすことができます。「これはやってはいけない]とか、「やったほうがいい」という判断もできるようになります。あとは「芸は身を助ける」ということですか。しみじみと身にしみて感じています(笑)。
お稽古に来る方に「とにかく続けなさい」と言っています。飲み込みの早い人、遅い人、個人差があります。十年経っても物になるかは分からないと言うと、「そんなに大変なのか」と思われて、お稽古に来なくなってしまいます。だから、いつも「頑張ってね」と言っています。
実際、子どもが十年お稽古するのと、大人になってからの十年は大きく違いますしね。
――優しくていらっしやる。
いけないんですよ、優しいのは。本当は厳しくしないと。私は、父にすごく厳しく教わってきましたが、今の人を見ていると、「この子は厳しくしたら来なくなってしまうかな」というところがあります。大丈夫だと思った子だけしか、叱れません。御身大切ではいけないと思っていますが、なかなか。嫌われたり、うるさがられたりするのを避けてしまいます。商業演劇などで舞台で踊る、そのときには厳しく「あなた、これでお金をもらうんでしょ。お金をもらうのなら、そのように勉強しなさい!」「お客様に見ていただくのでしょ!」と言っていますが。
――先生がお育ちになったころと人間そのものが違ってきていますでしょうし、何かを言っていただけることに感謝する人が少なくなりました。私たち人権擁護委員は活動の中で"地域力"の大切さを言っているだけに、お気持ちが分かります。
ご家庭では、どんなお父様なのでしょうか。
――仄聞したことなんですが、先生はちょっと目がお悪いとか。
緑内障なんです。二回、手術をしまして、片方はほとんど見えません。こちらは真ん中だけが生きています。老眼が入ってきていますけれども、ゆっくり時間をかければ、ポロポロとひろい読みぐらいならできます。平成二年の三月に治療を勧められ、「悪くなったら戻らない」と言われましたが、四月に舞台を控え、重要な役どころをいただいていましたし、そこまで進むとは思ってもいませんでした。それで五月になってから入院したら、そのときにはかなり悪くて。踊りに関しては、書いた譜面が読めなくなってしまって、譜面は倉庫に入っています。自分が踊る姿をビデオに録画して、見る方向を変えて、あっち透かし、そっち透かしで見ています。お芝居のときは、稽古初めの「読み合わせ」が大変です。十日問ぐらい前には台本をもらうので、それまでに一生懸命あらすじと自分の台詞を覚えています。つっかえたら、私の目のことを知っている親しい方が、ぱっと言ってくれます。初めてその光景を見たら、「何だ。こんなところでつっかえて」と思う方がたぶん多いと思います。でも、これはしょうがないなと。
――見た目で判断されることは辛いですね。
私は数えで四十二歳、本厄のときにそういう状態になったので、それまで自分が持っていた感覚がありますから、舞台に立っていますし、振り付けもしています。一緒にお稽古をしていて、ちょっと体の向きが違うと、「足、違うんじゃない」と言ったら、本当に違っている。もっと早くから目が悪くなっていたら、大変だったと思います。ただ、初めて行くところはちょっと怖いですね。段差があっても距離感がつかめません。だから「お先にどうぞ」と言われると困ります。 毎朝、神様と仏様にお参りさせていただくのですが、ライター(チャッカマン)でろうそくに火をつけるのに、最初にろうそくの芯を手で確認しておいて、そこにポンと火をつけます。
生活の智恵ですよね。見えにくいからできないというのではなく、見えにくかったら見えにくいなりに何とかできます。目が悪くなってから教わったこともたくさんあります(笑)。
――新しいことを始めるバイタリティーは、そういうところから来ているのかもしれませんね。認識を新たにしました。ありがとうございます。
確かにこうならなければ、"ゆかたde Shall we dance"も考えなかっただろうし、見えていたら、また違う方向で変わっていたかもしれませんが、今を大事にして生きたいですね。お芝居では、初めてのスターさん、初めてのスターさんじゃない若い子と出会います。様々な出会いがあるというのは、会社に行っていても同じですけれど、価値観の違う人達と接することができて良かったかなと。勉強になります。
それと、いろんな役ができます。踊りの場合は、白く塗って二枚目もできるし、悪党もできます。お芝居の場合は、違う人生を演じることができます。
――お一人で、いろいろな人生を、違う人間を演じることができるのは、そういうお仕事ならではのことですね。
人権擁護委員は、様々なご相談を受けながら人と接しています。お話を伺いながら一緒に考えて、その方が自分なりの解決方法を見つけたり、元気を出して生きていく手助けができればと活動していますが、人との出会いを大事にするという点では、底流でつながっているように思います。
これから、四月には京都南座で『藤山直美公演・春風物語〜恋の呂昇』、十月には中日劇場で『最後の忠臣蔵』が控えています。お客様に、「心に響いた」「観て良かった」と言っていただけるようなお芝居にしたいと思っています。
いい演技をするためにも、足腰を鍛えておかなくてはなりません。座ったら立てない、というわけにはいきません(笑)。
――どうぞお体をお大事になさって、お励みくださいますよう。大勢のみなさんに夢や喜びをたくさん分けていただけたら、うれしく思います。
今日はご多用の中を、ありがとうございました。
|
人権のひろばNo.73掲載記事 『中将姫誓願桜』 春風物語「恋の呂昇(ろしょう)」 メディアページに戻る |
| TOP | ごあいさつ | プロフィール | 林流について | 近況報告 |
| 今後の活動 | 舞姿 | お稽古教室 | ワークショップ | 林流 こどもをどり塾 |
| 啓二の会 | お問い合わせ | 更新履歴 | メディア | ブログ |
| 今後の活動 | 舞姿 | お稽古教室 | ワークショップ | 林流 こどもをどり塾 |
| 啓二の会 | お問い合わせ | 更新履歴 | メディア | ブログ |
このサイトに掲載の記事・写真・音楽等の無断転載を禁じます。